
ようこそ☺︎
お越しいただき、ありがとうございます。
このブログを執筆している、クロマク・リヒトと申します。
どうぞ「リヒト」と呼んでくださいね☺︎
こちらは、読書感想を綴る【読書ノート】です。
今回ご紹介するのは、「ミニマリスト」に関する本、日米ベストセラー《より少ない生き方》の実践編、《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》です。
最近、YouTubeやテレビでも話題の「ミニマリスト」。
- 「ミニマリストのあの人の真似をしてみたけど、しっくりこない…」
- 「あれもこれも捨ててみたけど、空いたスペースにまた何かを入れたくなる」
- 「物欲が止まらない。最新ものが欲しくなる」
こんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
ミニマリストを目指すすべての人の必読書!
── エマ・ロエベ
ガラクタが減れば、心の豊かさが増える。
── ケイト・フランダース
この本が貴重なロードマップになるだろう。
── ケイティ・ウェルズ
《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》「推薦の言葉」より
\\\こんな方におすすめです///
- 前著「より少ない生き方」を読んだ方
- ミニマリストに憧れている方
- ミニマリストとして、わが家を好きな場所にしたい方
- モノへの執着の手放し方を知りたい方
- 海外のミニマリスト事情について知りたい方

それでは、《より少ない生き方 ものを手放して豊かになる》の感想ページへ、ご案内します。
- 《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》の基本情報
- 《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》の読書感想
- 《第1章 ミニマリズムでわが家を大改造する》の読書感想
- 《第2章 ものを減らして豊かになる「ベッカー・メソッド」》の読書感想
- 《第3章 家族で過ごす時間を取り戻す》の読書感想
- 《第4章 心地よく休息して健康になる》の読書感想
- 《第5章 自分らしいスタイルを見つけて維持する》の読書感想
- 《第6章 機能を優先して家族の清潔さを保つ》の読書感想
- 《第7章 食事を楽しみ「おもてなしの心」を育む》の読書感想
- 《第8章 ストレスをなくし頭脳を解放する》の読書感想
- 《第9章 過去に別れを告げるとき》の読書感想
- 《第10章 わが家の見た目を変えて理想に近づける》の読書感想
- 《第11章 小さな提案》の読書感想
- 《第12章 ミニマリズムはすべてを変える》の読書感想
- まとめ
《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》の基本情報
※広告◇《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》の概要
[タイトル]より少ない家大全 あらゆることから自由になれる
[著者]ジョシュア・ベッカー
[訳者]桜田 直美
[出版社]株式会社かんき出版
[ジャンル]人生論・教訓
[出版年]2022年11月21日
◇《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》の内容
日米ベストセラー
『より少ない生き方』の実践編!!
リビング クローゼット キッチン
バスルーム 子供部屋 etc
誰もが部屋ごとに迷わずものを手放せる!「片づけのプロセスを誰でもできる簡単なステップで教えてくれる。
ミニマリストを目指すすべての人の必読書!」
――エマ・ロエベ (MindBodyGreen.com ホームエディター)「これは単なる片づけの本ではない。
それぞれの部屋が何のためにあるのかを思い出し、
わが家を地球上でいちばん大切な場所だと感じられるようになることが目的だ。
ガラクタが減れば、 心の豊かさが増える」
――ケイト・フランダース (『The Year of Less』著者)「ジョシュアの文章は楽観的で心地よく、 優しく読者の背中を押してくれる。
家の中をすっきりさせたい、
人生のコントロールを取り戻したいと思っているなら、
この本が貴重なロードマップになるだろう」
――ケイティ・ウェルズ (WellnessMama.com 設立者)考え方を変えてみよう!
自宅に満足できないのは、
ものが足りないからでも、
整理整頓ができないからでもない。
根本の原因は、
誰かに押しつけられた「理想の家」に
囚われているからだ。
たくさんのものを持たないだけでなく、
たくさんのものを欲しがらないようになると、
穏やかで満ち足りた心が手に入る。
つねに最新のガジェットを追いかけている人や、
家具を買いあさっている人たちには、
とうてい到達できない境地だ。全世界で2000万人を幸せにした
引用:かんき出版《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》公式サイト「書籍情報」より
ものに囚われず豊かな人生を手にする方法が、
ついに日本上陸!

ここからは、私自身の読書感想が続きます。
もし本の内容に興味を持たれた方は、ぜひ実際に手に取ってみてくださいね。
個人的に心に残った点や、特に印象的だった部分についてお話ししていきます。
※広告
《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》の読書感想

《第1章 ミニマリズムでわが家を大改造する》の読書感想
目次をパラパラ読んでいると、『PART2の付録』が気になった。“付録”って言葉がなんとなく昔から好きだったからかな(笑)おもしろそうだと感じた。

21ページ〜[▫️驚くべき7つの事実──ものを持ちすぎていることの証明]の最後の7つ目に、
私たちは一生のうちに、何かを探すことにトータルで3,680時間(153日)を費やしている。探しもののリストの上位に入るのは、携帯電話、鍵、サングラス、そして書類だ。
と書かれていた。
時間(日数)の多さにもびっくりしたけど、「探しものリスト」の上位にある“携帯電話、鍵、サングラス、書類”の中で、「書類はわかるけど、携帯電話って探すものなんだ🙄」と思った。笑
私は、ものの置き場所は大体決まっているから、「あれどこやったっけ?」「これどこ置いた?」となることはあまりない。
強いて言うなら、自分の書いたメモの“どの位置に書いたか”を探すくらいかな。覚えてないだけかもしれないけど。笑

23ページ〜[誰でも人生を向上させられる方法]の章で、著者のジョシュアが「ミニマリズム」についてこう語っていました。
私が考える「ミニマリズム」の定義は、「自分にとってもっとも大切な価値観を最優先して、その価値を妨げるものをすべて排除すること」となる。
この1文を読んで、「あれ?これ、繊細さん(HSP)の本でも似たようなことが書かれてたな」と思い出しました。
たしか、「自分の“〇〇したい”を大切にすると、人生が変わる」っていう内容だった気がする。

26ページの、
あなたが今住んでいる家を選んだのには、何か理由があるはずだ。その中には「気に入ったから」という理由もあるだろう。少なくとも、自分のものにして手を加えれば気に入るはずだという思惑があったのではないだろうか。
という文章があり、それに思わず心の中でツッコミを入れた。
「いや、前の職場の人間関係につまずいて、逃げるように地元に帰ってきたんだよ…😂」と。
うーん🙄。この感想まとめてて、ちょっと悲しくなってきた(笑)
《第2章 ものを減らして豊かになる「ベッカー・メソッド」》の読書感想

41ページ〜[ベッカー・メソッド]で、
『 1 ミニマル化のプロセスを始める前に、まず自宅をどうしたいか、人生で何を目指すのかという目標を決める』
と書かれていた。
私が前から思っているのは、「いつ死んでもいいように、片づけておきたい」ということ。
次の項目には、
『 2 家族と一緒に住んでいる人は、これを家族のプロジェクトにする』
とあって、「これは無理だな。自立して、早くここから出て行きたいし」と思った。
「引っ越しをする(ここから出ていく)ためにも、片づけたほうがよさそうだ」と思った。

42ページ〜[目標を持ってものを減らす]の章の中に出てきた〔死ぬまでにやりたいことリスト〕の中に、『・紅海でスキューバダイビングをする』という項目があった。
「紅海」ってなんて読むんだろう?と気になって調べてみたら、「こうかい」と読むらしい。
そして、「紅海」は、アフリカ東北部と、アラビア半島に挟まれた湾であって、「紅く」なかった(笑)

48ページ〜[家族と話さなければならないこと]の章。
著者のジョシュアが「ミニマリストになる」と母親に伝えたときの会話に、こんな1節がありました。
「嘘でしょう、ジョシュア」と、母は言った。「さっきテレビでオプラ・ウィンフリーがミニマリストにインタビューしていたんだけど、あの人たちは食べ物をスーパーで買わないでゴミ箱から拾ってくるのよ」
……「ものすごい偏見がある(😂)」と思わずクスッと笑ってしまった。

56ページ〜[簡単な場所から難しい場所]の章。
『8 ガレージと庭』が最後に出てきたけれど、私はアパート暮らしなので、ガレージも庭もない。
……ということは、私にとって「1番難しい場所」は存在しないってことかな?
ガレージって、なんだか“ザ・アメリカ”って感じがする。🇺🇸
強いて言えば、私の場合は「ベランダ」なのかもしれない。🙄
《第3章 家族で過ごす時間を取り戻す》の読書感想
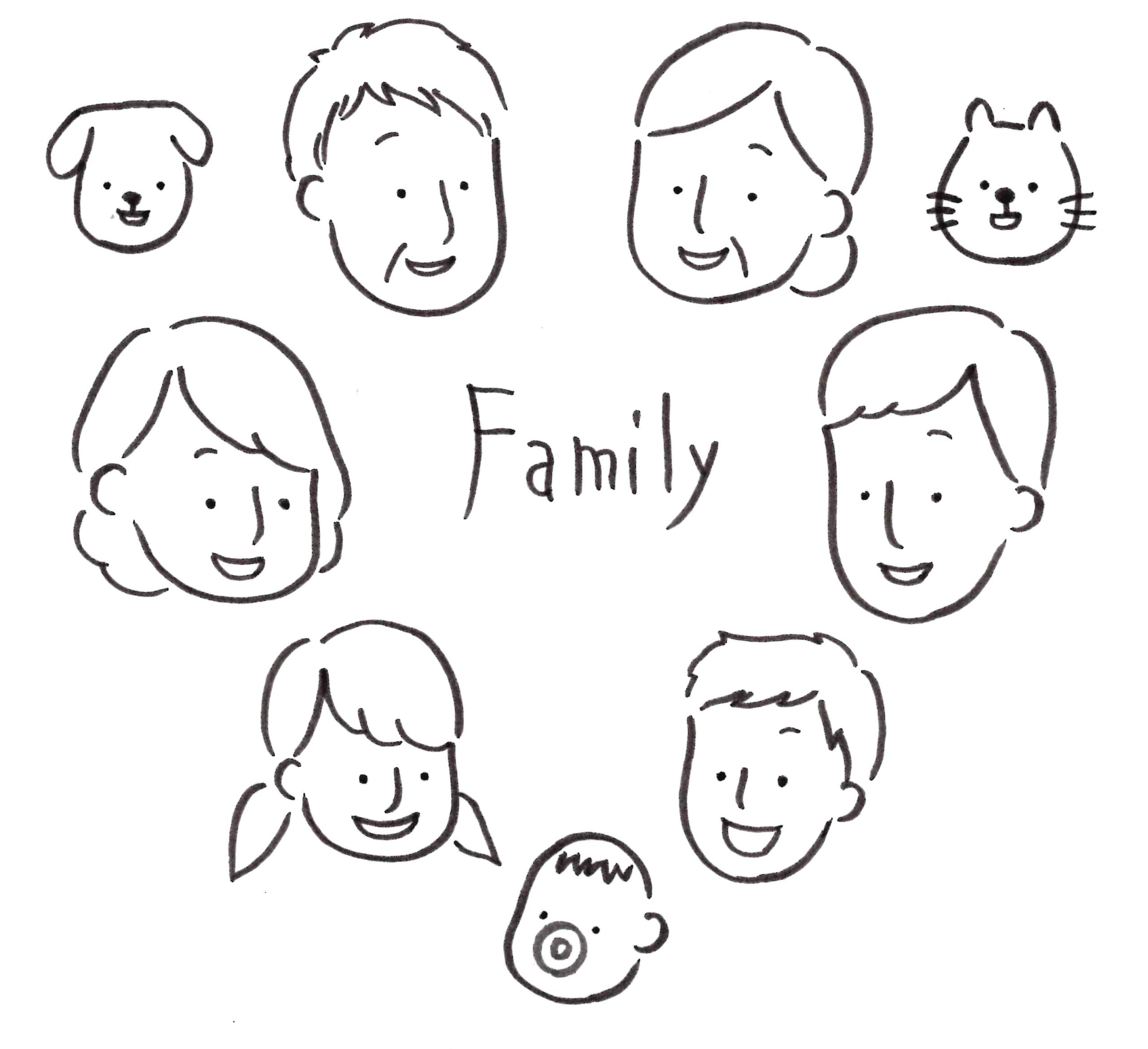
83ページ〜[理想のリビングルームを思い描く]の章に、リビング・ダイニング・キッチンの機能を組み合わせた「グレートルーム」という単語が出てきた。
この「グレートルーム」という言葉を見たとき、ゲームの『都市伝説解体センター』に出てくる「グレートリセット」が思い浮かんで、「カッコいい🤩」と感じた。
そこで調べてみたら、実際はめちゃくちゃ広い会議室みたいな空間で、「これはちょっと落ち着かないかも🙄」と思ってしまった。笑

89ページ〜[◆リビングルームをミニマル化する]の章にある『4 収納エリアを深掘りする』で、「抜本的」という言葉が出てきた。
読み方や意味がよくわからなかったので調べてみた。笑
「抜本」は「ばっぽん」と読み(合ってた🤭)、問題や状況を根本から解決しようとする態度や行動を指す言葉だそう。
そして、93ページの『ソファにかけるブランケット』という1文を、なぜか「ソファになりかけているブランケット」と読み間違えてしまい、想像したらおもしろくて(🤣)笑うところじゃないのに、思わずクスッと笑ってしまった。
《第4章 心地よく休息して健康になる》の読書感想

102ページ〜[寝室のミニマル化]の章に出てきた「キチネット」という言葉。(前にも調べたような気がするが😅)
改めて調べてみたところ、「簡易キッチン」のことを指すらしい。
……やっぱり前にも調べた気がする🙄笑

105ページ〜[◼︎心が落ち着き、健康になった──ミニマリストの告白]に書かれていた、最後の1節が「いいな」と思った。
ミニマリストになってからは、自分の新しい一面を毎日のように発見しています。私にとって、ミニマリズムは人生と同じ。それは現在進行形の旅です。
「自分の新しい一面」──つまり、“自分の可能性”に気づけるということなんだと思う。その考え方に、なんだかワクワクした。

109ページ〜[◆寝室をミニマル化する]の章にある『7 家具を処分する(もし可能なら)』の1節。
寝室には5つの家具があった。ベッド1台、引き出し収納1台、ナイトスタンド2台、そして大きな洋服箪笥1台だ。そのうえ、箪笥の上にはテレビが置いてあった。
……想像したら、「見づらい🤣」と小さく笑ってしまった。

122ページ〜[すこやかな眠りを確保する]の章で、『もっとも睡眠時間が少ない国は日本だ。』と書かれていて、「やっぱり少ないんだな」と改めて実感し、少し残念な気持ちになった。
《第5章 自分らしいスタイルを見つけて維持する》の読書感想

126ページ~[クローゼットのミニマル化]の章で、「服装のアイコン化」について書かれていた1節。
いつもの服装でいることは、「私は自分の人生の主人公になる」という宣言と同じだ。
「マンガの登場人物がいつも同じ服装なのもそのためだ。(略)」
この部分を読んだとき、脳裏に浮かんだのは──ドラえもんに出てくる、黄色い長袖の「のび太」でした。笑
たしかに、彼も見事に“アイコン化”している……🤣

人物で「アイコン化している」と聞いて真っ先に思い浮かべたのは、Appleの創設者、スティーブ・ジョブズ。
黒のハイネックにジーンズ、スニーカー。彼もまさに“アイコン化”している。
私も、今年の夏は服を少し単純化してみた。
Tシャツ(コットン100%)は黒、ボトムスも黒のストレッチパンツ。いわば全身「まっくろくろすけ」🤭
その分、小物(帽子やカバン)はベージュやアイボリーにして、少し軽さを出した。
やってみて思ったのは、選択肢を減らすと本当に楽になるということ。
今は秋冬服をどうしようか考え中。
お気に入りのトレーナーをうまく使いつつ、できればインナーも新しく取り入れたいなと思っている。

142ページ〜[◆クローゼットをミニマル化する]に出てきた『ディドロ効果』──「新しく買ったものに合わせて他の持ち物も統一したくなり、次々と新しい物を買ってしまう」という心理現象。
確かに「シャンプーやスキンケアを全部そのシリーズで揃えたくなるなぁ🙄」と思った。
また、ハンドメイドでも、色違いで欲しくなったり、作りたくなったりもするし。笑
これが『ディドロ効果』で、「物が物を呼ぶ」正体なのかもしれない。(🤯)

153ページ〜[家の外と中をつなぐスペース(マッドルーム)]の章に出てきた「マッドルーム」。うちにはないので、調べてみた。
「マッドルーム(mudroom)」とは、主に欧米の住宅に見られる“泥の部屋”という意味のスペースで、屋外から帰ってきたときに、汚れた靴やコートを脱いで整理し、室内に汚れを持ち込まないようにするための玄関に併設された空間だそう。
画像も見てみたけれど、どれもおしゃれでびっくり。
犬の散歩から帰ってきて、そこで足を拭いたりするのかな?🙄?
……やっぱりアメリカの家は広い。🇺🇸
《第6章 機能を優先して家族の清潔さを保つ》の読書感想
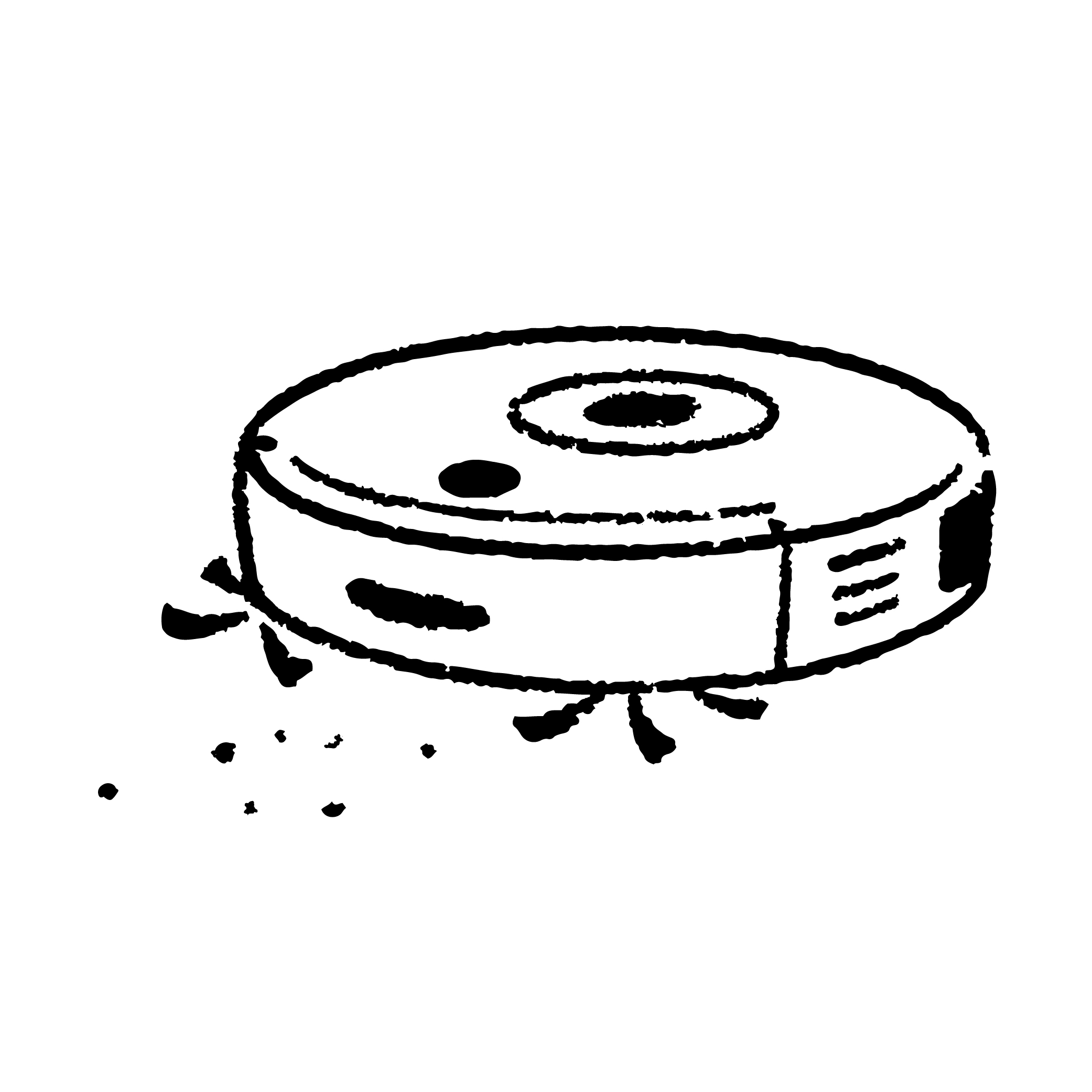
160ページ〜[お風呂を癒しの場所にする]の章に出てきた『ホウ砂』が何なのか分からなかったので、調べてみた。
ホウ砂(ホウシャ)とは、天然のホウ酸ナトリウム鉱石を精製したもので、主に乾燥剤や除草剤、家庭用クリーナーとして使われる物質なのだそう。さらに、スライムの材料としても知られているらしい。え🤯知らなかった。笑

163ページ〜[◆バスルームをミニマル化する]の章の『1 洗面所の戸棚を整理する』で、「処方薬」や「市販薬」などの“医薬品を整理しよう”とあって、「海外では“洗面所”の戸棚に医薬品を置いているんだ」と、ちょっと驚いた。薬箱って、日本だけの文化なのかしら?
そして『2 美容製品を減らす』では、
「女性は平均して実に40点もの化粧品を所有している。(中略)さらに衝撃的なのは、その40点のうち実際に使用するのは平均してわずか5点しかないという事実だ。
というところにビックリ。もったいない…😳って思った。

173ページ〜[シンプル・イズ・ビューティフル]の章に出てきた『カウンターカルチャー』という言葉、知らなかったので調べてみた。
「カウンターカルチャーとは、社会の主流文化に対して反対的な価値観や行動様式を持つ文化のこと。若者やサブカルチャー層を中心に、既存の社会規範や価値観に抵抗し、独自の文化を創造する動きを指す」らしい。
……「陰謀論だ!」とかデモとか、そういう感じ?🤯
《第7章 食事を楽しみ「おもてなしの心」を育む》の読書感想
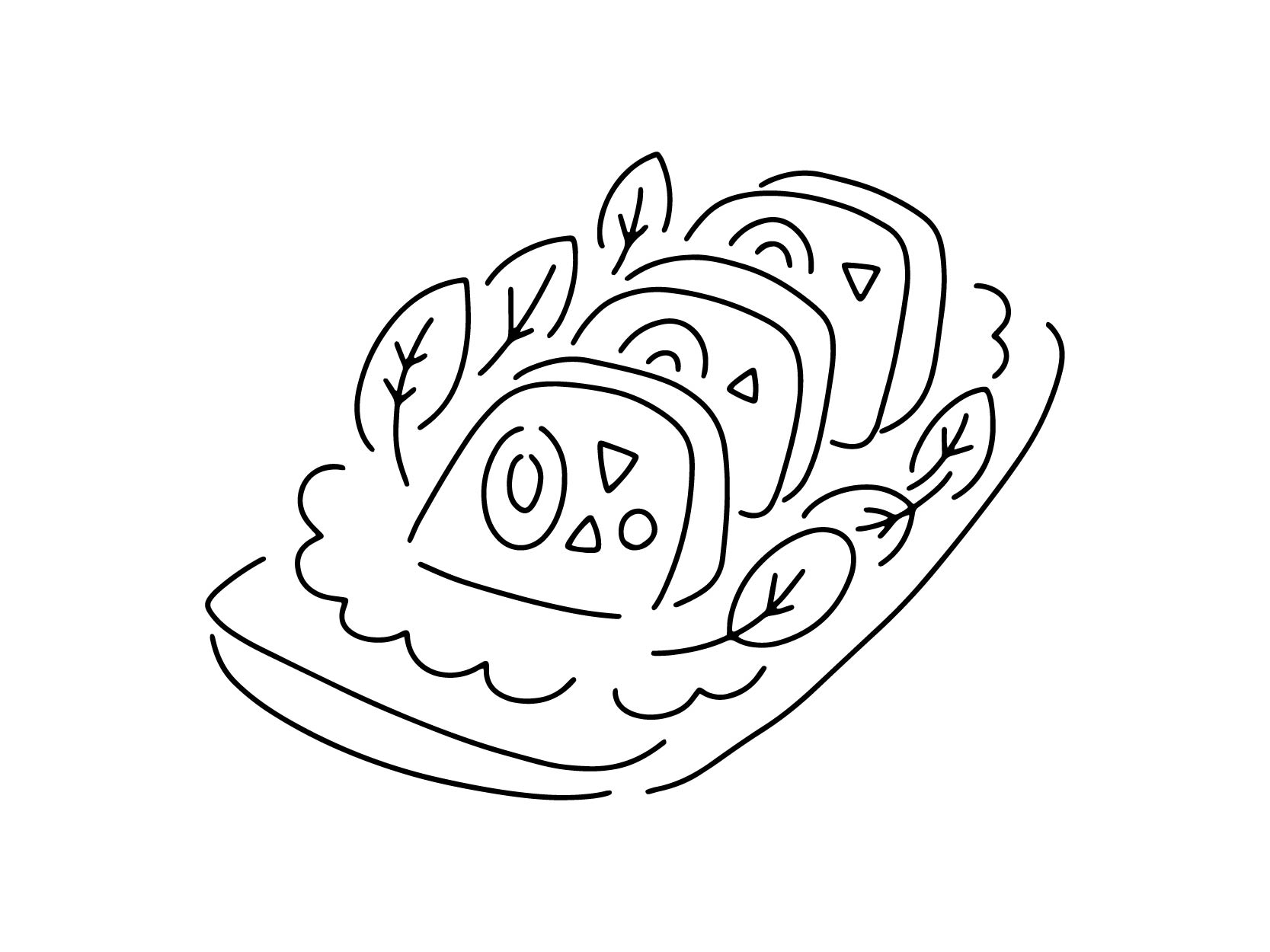
193ページ〜[ミニマリスト・シェフの教え]の章に出てきた『キッチンに必要なもののすべて』というリストに、「穴じゃくし」というものが登場した。
「穴じゃくし」ってなんだろう?と気になって調べてみたら、「穴あきおたま」のことだった。
そして「じゃくし」は漢字で「杓子」と書くらしく、「杓子(しゃくし)」は、液体やごはんを“すくう”ための道具の総称なんだとか。
例えば、“しゃもじ”は「飯杓子(めしじゃくし)」というらしい。
あと打ち水に使うアレ、「柄杓(ひしゃく)」も、「杓子」の仲間なのだそう。深い…(🫣)。

197ページ〜[◆キッチンをミニマル化する]の章の、3つ目の原則『2つ以上あるもの、めったに使わないものを処分する』で、『食用品保存容器について(略)入れ子式になっているものは残すこと』という文があった。
『入れ子式』がわからなかったので調べてみた。
マトリョーシカ🪆みたいな入れ物のことだとわかって、「ああ、そういうのは残していいんだな」と納得。
……と思ったけど、そもそも持っている保存容器は、てんでばらばらだった。笑
《第8章 ストレスをなくし頭脳を解放する》の読書感想
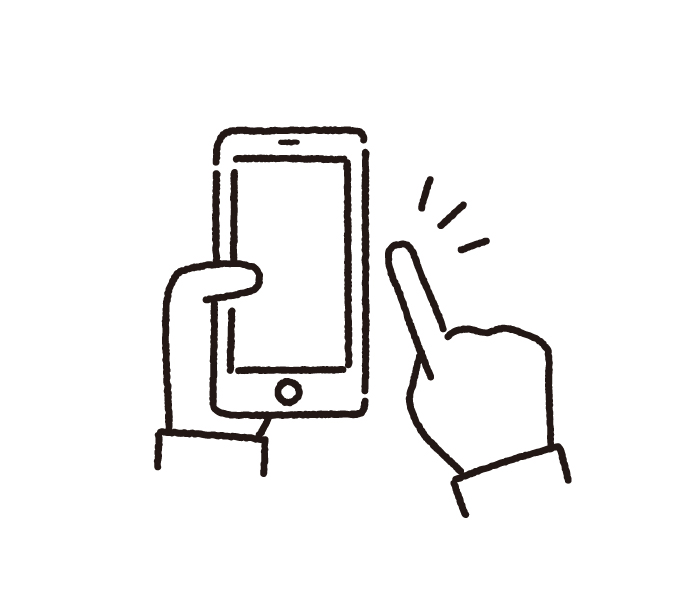
217ページ〜[◆ホームオフィスをミニマル化する]の章を読んで。
ホームオフィスをミニマル化する前に、まず自分にとっての理想のホームオフィスを明確に思い描く。
私の理想のホームオフィスは、「作業部屋かな?」と思った。
ハンドメイドができる作業台(ダイニングテーブル)で作業をして、パソコンもそこで使用。
たまに休憩するためにローテーブルを置き、お茶を飲む時間も楽しむ。あと、小さな本棚も置きたい。
少しずつだけれど、こういう理想に近づいてきている気がする。

230ページ〜[デジタルのガラクタをどうするか]の章に出てきた『Poke』が何かわからなかったので調べてみた。
「Poke(ポーク)」とは、英語で「つつく」や「突き刺す」といった意味を持つ動詞だそう。
たとえば、長時間視聴してくれているのに反応がないリスナーに、「ねぇねぇ」の意味を込めて、ツンツンすることを「“Poke”する」というらしい。はへぇ😳
鬼滅のしのぶさんが義勇さんにツンツンしてる扉絵を思い出した。笑

231ページ〜[デジタルのガラクタをどうするか]の章で、イギリス人のクレイグ・リンクさんの言葉の中に「今日性」という言葉が出てきた。
読んでいて引っかかったので、調べてみた。笑
「今日性(こんにちせい)」とは、物事が現在の時勢や現代社会と深く結びついているさまを表す言葉だそう。
本来は「現代性」の意味を指すようですが、時代の移り変わりがあまりにも速いため、単に「現代性」では幅がありすぎる。
そこで、「今の今」という意味で解釈されたのではないかとのこと。(🤯)
《第9章 過去に別れを告げるとき》の読書感想
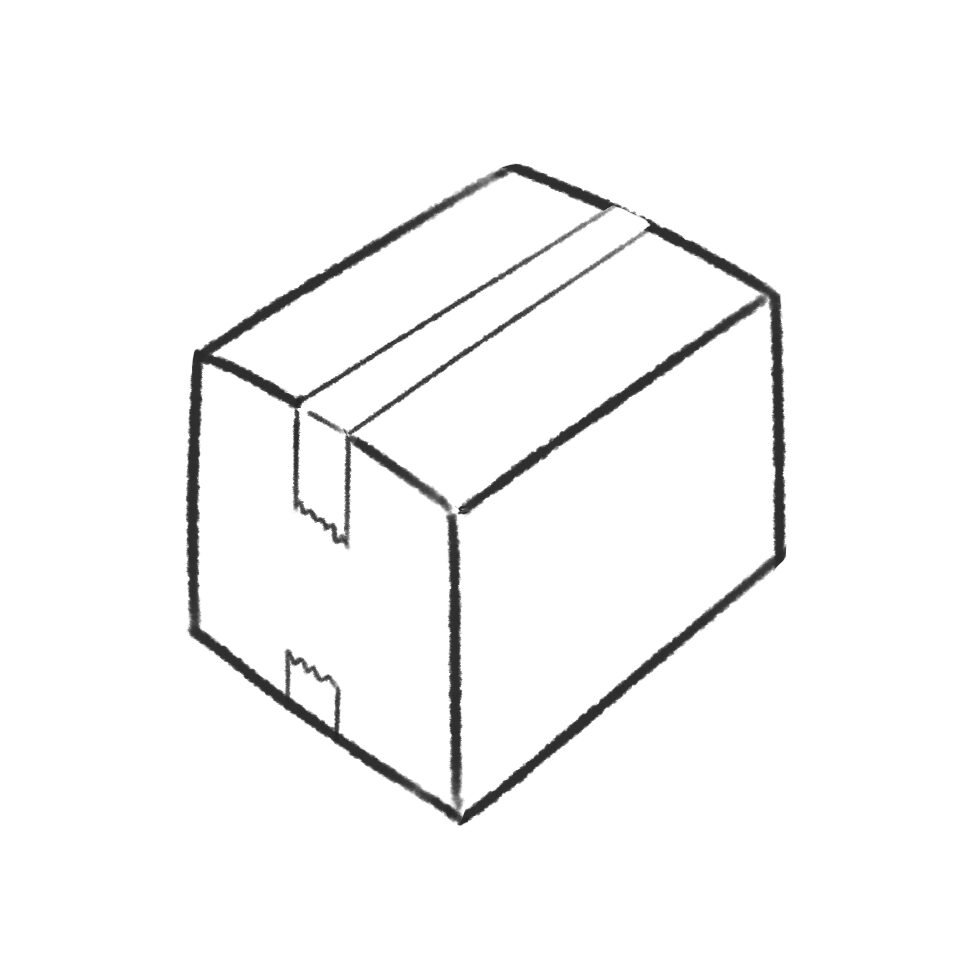
239ページ〜[物置とおもちゃ部屋のミニマル化]の章。
所有物は家のいたるところにある。なかでも特に集まりやすいのが、屋根裏や地下室、物置などだ。
うちには屋根裏も地下室もない。物置なら、小さなものがひとつある。賃貸に備え付けられているもの。その中には冬用のタイヤを入れている。
屋根裏部屋や地下室は、日本の家というより、やっぱり海外っぽいなぁと思った。
想像したのは、広々としたバイオハザードの洋館のような感じのもの。
私はどちらかというと、狭めの秘密基地みたいな屋根裏や地下室に少し憧れる🤭

241ページの1節、
人間には「場所があればとりあえず詰め込む」習慣があると言うことだ。
を読んで、思わず「ね😂(わかる)」と小さく頷いてしまった。笑
隙間があると埋めたくなるのは、やっぱり人間の習性なんだなぁ…(😅)と思った。笑

245ページ〜[◆物置部屋をみにまるかする]の章にある『5 思い出の品を厳選する』の1節。
ここでのコツの1つは、手放すものの写真を撮ることだ。そもそも本当の思い出は、その「もの」ではなく自分の中にある。
これを読んで、思い浮かんだのがミニマリストのしぶさんと、同じくミニマリストのタケルさんのYouTube動画。
確かに、写真を撮ったら手放せる人もいたし、私もたぶん写真を撮ったら捨てられると思う。
そして、思い出は「自分の中にある」と、改めてしみじみ感じた。

250ページの1節、
故人のものを捨てずにとっておくことが、故人への敬意につながるという考えもある。しかし、ここで考えてみよう。(略)自分を愛してくれた故人を大切にするいちばんの方法は、自分ができるかぎり最高の人生を送ることであり、故人の持ち物に押しつぶされることではない。
これを読んで、思わずうるっとしてしまった。
さらにそのあとに続く、
自分の過去もそれと同じだ。(略)今を十分に楽しむべきだ。
特にこの『今を十分に楽しむ』を読んだとき、なんとなく心が明るくなったような感じがした。

255ページ〜[実現しなかったキャンプ旅行]の章を読んで、ずっとうるうるしっぱなしだった。笑
ティムとリサ・タワー夫妻の言葉:
「子供たちを連れて定期的にキャンプ旅行に出かけるのが夢だった」
「子どもたちが大きくなると、スケジュールを調整するのがさらに難しくなった。そしてついに時間切れに(略)」
「キャンプ用品を見るたびに胸が痛む。そこには、子どもたちと一緒につくれたかもしれない思い出が詰まっている。でも今となっては、すべてが手遅れだ」
これを読んで、先ほどの感想と同じく、「今を十分に楽しむ」ことに集中した方が、後悔は少なくなるのかなと思った。
《第10章 わが家の見た目を変えて理想に近づける》の読書感想

293ページ〜(PART2の付録)[ミニマリストのためのメンテナンスガイド]で、「幅木」という言葉が出てきたので調べてみた。
「壁と床の接合部に設置される横板材」とわかり、家の壁と床の間に目を向けると、確かにあった。「お前か!」とちょっとだけ楽しくなった。笑

301ページ〜[▫️贈り物の習慣を考え直す]に出てきた『バル・ミツバ』という言葉が気になったので、調べてみた。
どうやら「ユダヤ教の成人式」のことらしい。
ユダヤ教では、男の子が13歳になると「バル・ミツバ」、女の子は12歳になると「バト・ミツバ」という儀式を行うそう。
どちらも「戒律を守る責任を持つ年齢に達した」という意味があるとのこと。
ここで言う「成人」というのは、日本でいうような「結婚できる年齢」や「選挙権がある」といった意味ではなく、「神様の前で善悪を判断し、責任ある行動ができる年齢になった」ということを表しているらしい。
宗教的な観点ならではの“成人”なんだなと思った。
贈り物の習慣の話の中で紹介されていたこの儀式、文化や価値観の違いが垣間見えてとても興味深かった。おもしろ。
《第11章 小さな提案》の読書感想
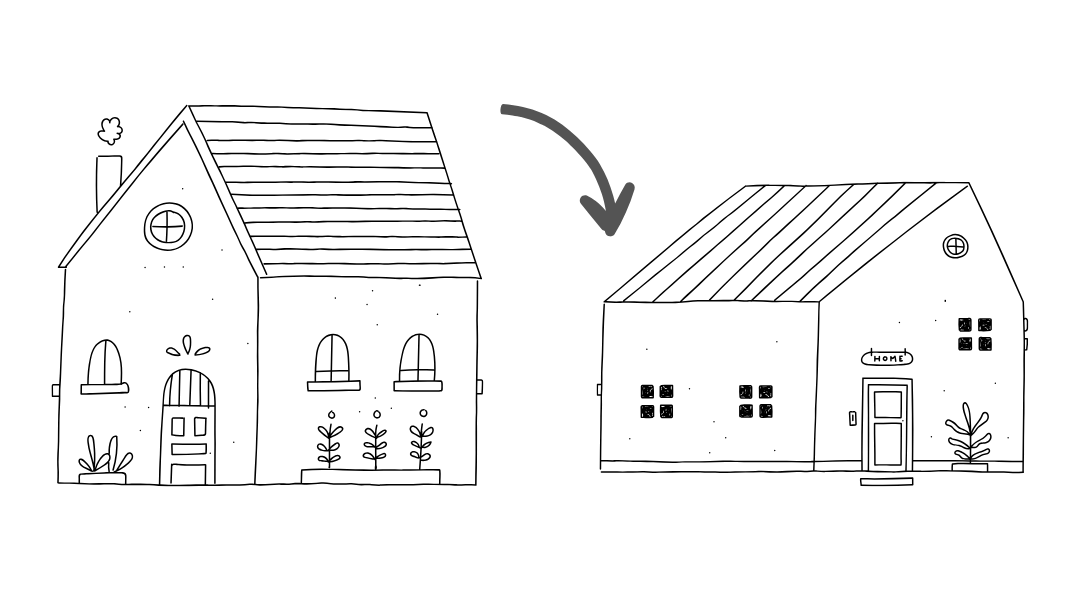
321ページ〜[小さな家に引っ越す]の章を読んで思ったこと。
部屋の数は、できれば2LDKがいいなと思った。
寝室と作業部屋(この本でいう「オフィスルーム」かな?😄)は、できるだけ別々にしたい。
寝室は“寝るだけの部屋”にして、スマホやタブレットは持ち込まない。だから本当に寝るだけの空間。6畳より小さくてもいいかもしれない。
作業部屋とリビングは一緒でもいいかな?と思ったけど、食事する場所と作業する場所は分けたい気もする。……匂いが移りそうだし。🙄
うーん、これじゃあ、家のダウンサイジングは難しいかも😅

324ページ〜[後悔はまったくない]の章を読んで、ケイ・エメリーさんの最後の言葉にうるっとした。
後悔していることがあるとすれば、もっと早く引っ越さなかったことね。夫が健康のうちに暮らしをダウンサイズしてたら、新しく手に入れた自由を一緒に楽しむことができたのにと思う。
著者のジョシュアさん夫妻もそうだけど、この本に登場するご夫婦は、みんな仲が良くて、お互いを大切にしていて、読んでいて胸があたたかくなる。
「いいなぁ」と思ったら、またウルウルしてしまった。笑
《第12章 ミニマリズムはすべてを変える》の読書感想
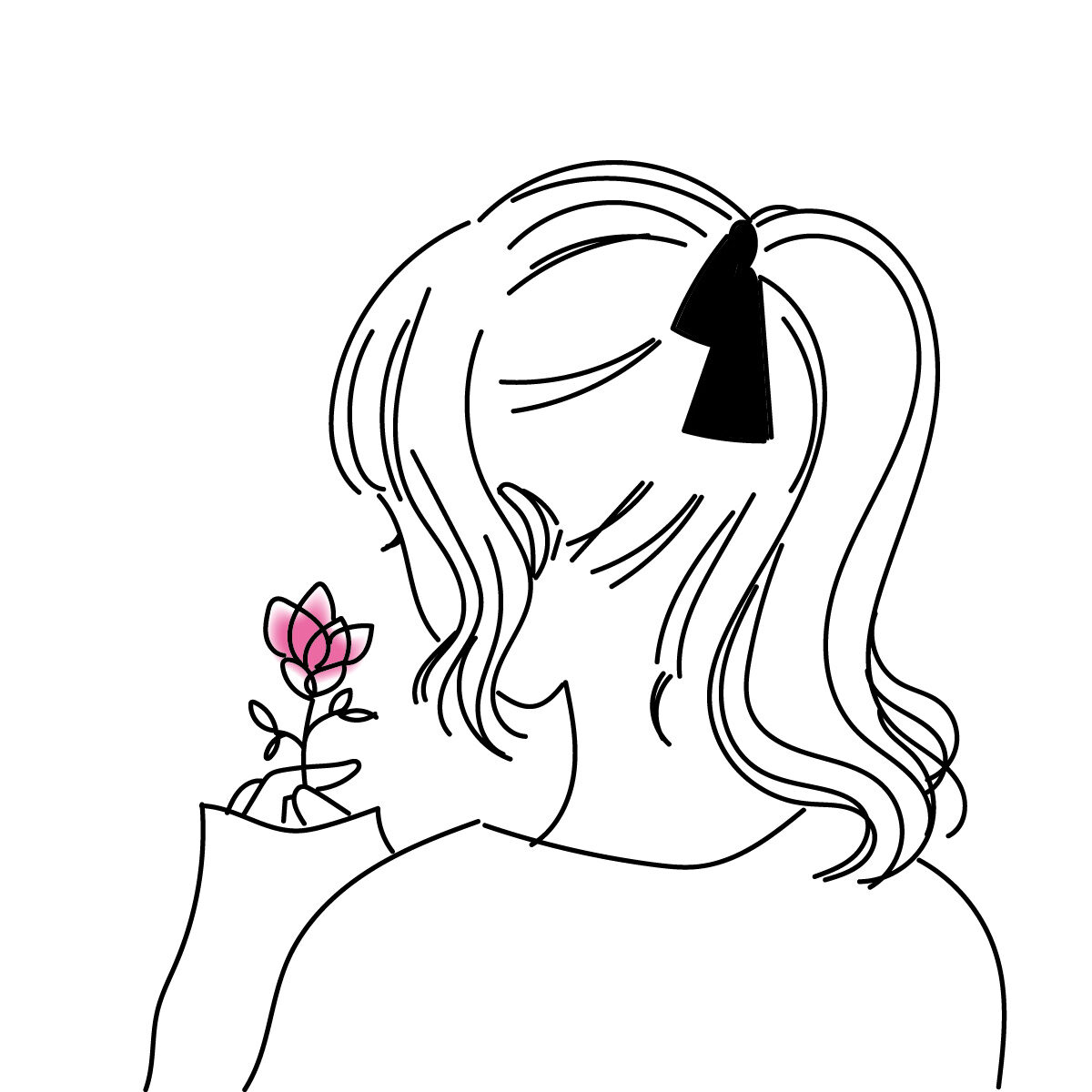
345ページ〜[人生の新しい可能性]の章に出てきた「敬虔(けいけん)」という言葉の意味がわからなかったので調べてみた。
「敬虔」とは、深く敬って態度をつつしむこと。特に、神仏に対してつつしんで仕えることを指す言葉だった。
本文では『私は敬虔なクリスチャン』と書かれていたので、著者のジョシュアさんは、神を深く敬い、信仰に真摯に向き合うキリスト教徒ということ。
そのあとに続く言葉も素敵だなと思った。
仕事は人々の人生に前向きな変化を起こす手段であり、そして余暇の時間は大切な人たちと一緒にすごすことを楽しむためにある。
特に「大切な人たちと」という部分がいいなと思った。
そういう考え(価値観)を持った家族のもとに生まれたかったし、私自身もそうなりたかった。(ちょっと悲しくなってきた😂)

354ページ〜[◼︎あなたはどんなことで感謝されたいか?]の章の質問。
『人生の終わりに、自分はどんなことで感謝されたいか』
その質問について自分なりに考えてみたけれど、具体的なことは思いつかず、「〇〇さんのおかげで」までしか言葉が出てこなかった。
でも絞り出してみたら、「〇〇さんに会えたことが幸せでした」と出てきて、なんだか鬼滅っぽいなと思ったら、ちょっとウルウルしてきた🥹笑

359ページ〜[◆残りの人生を最大化する]の章『1 自分自身のポテンシャルを知る』の1節。
第2章で、私が自宅のミニマル化に挑戦するあなたに送った言葉を覚えているだろうか?それは「あなたならできる!」だった。そして今、ミニマリズムの恩恵を最大限に活用しようとしているあなたに、私はまた同じ言葉を送りたい。あなたなら、できる。
うるうるした🥹笑

362ページ〜『3 正しいときに「ノー」と言えるようになる』の『・思いやり』の1節。
「欲しい、欲しい、欲しい」という生き方を脱した人は、「与える、与える、与える」という生き方を始めることができる。あなたはその思いやり深さで、この干からびた世界に水を与える存在になるだろう。
与える人になれるのかなと思って、「この干からびた世界に」のところでもうるうるした。笑
まとめ
今回の「読書ノート」は、《より少ない家大全 あらゆることから自由になれる》をご紹介しました☺︎
最初に読んだときは、前著「より少ない生き方」の方がおもしろい印象でしたが、2回目に読み返してみると(読書ノートの感想が所々抜けていたため😅)、新たな発見がいくつもあり、とても楽しかったです。
前著は入門編で、今回の「より少ない家大全」は、実践編という理解が深まった気がします。
本は何回読み直しても、前には気づかなかったことに気づけるのでおもしろい。まるでミニマリストみたいだな、とも思いました。
第4章にも書かれていた
ミニマリストになってからは、自分の新しい一面を毎日のように発見しています。私にとって、ミニマリズムは人生と同じ。それは現在進行形の旅です。
この1節が、2回目に読んだときに新たな発見となりました。
読書って本当に楽しい。前著と同様に、読んでいてワクワクしたり、時にはうるっとしたり、とてもおもしろかったです。
また少ししたら読み直そうと思います。
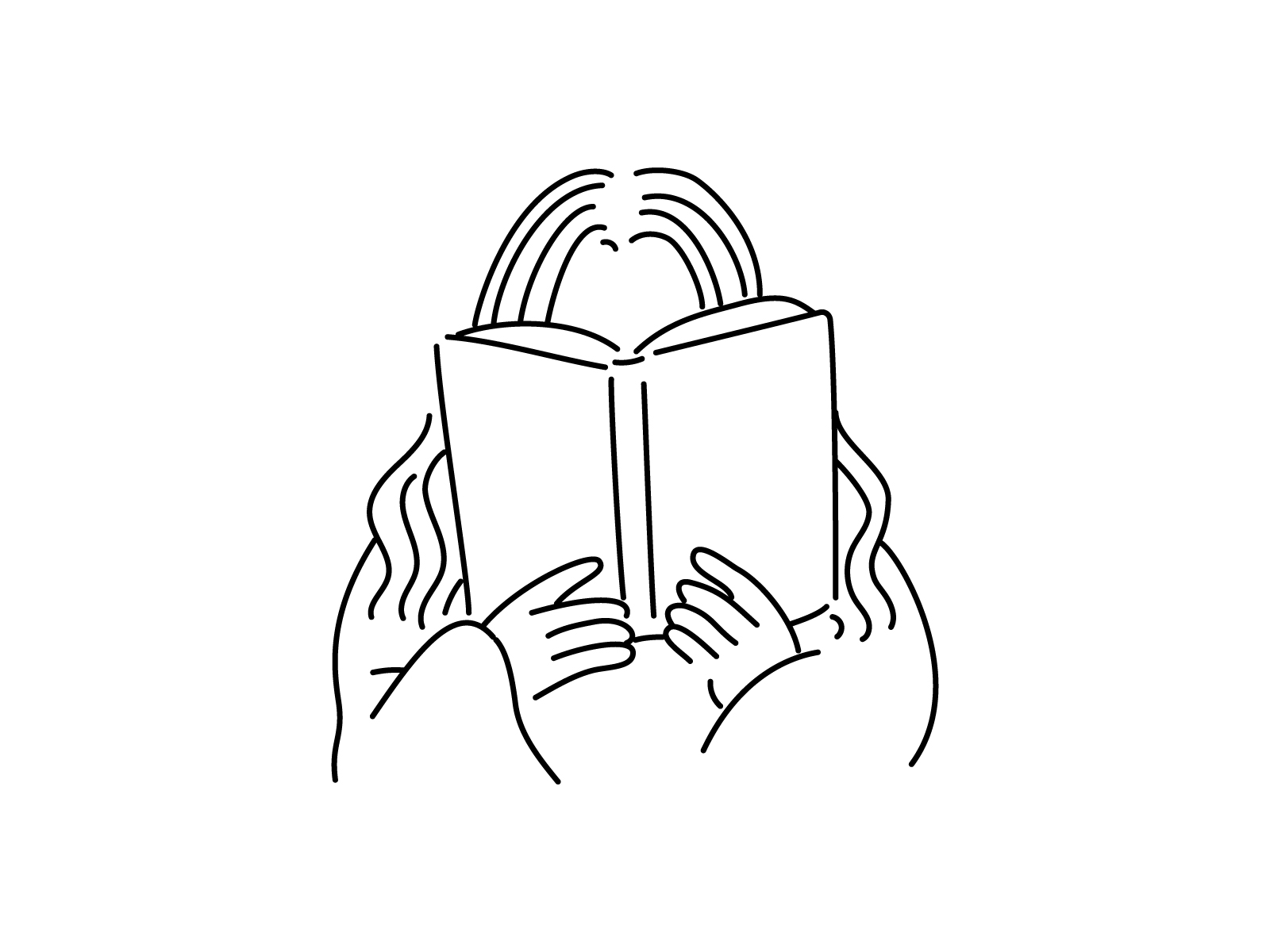

私の読書感想が、この広い世界のどこかで、誰かの役に立ったり、ちょっとしたヒントになれたら嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました☺︎♡
それではまた、本の世界【5ページ目】でお会いしましょう。
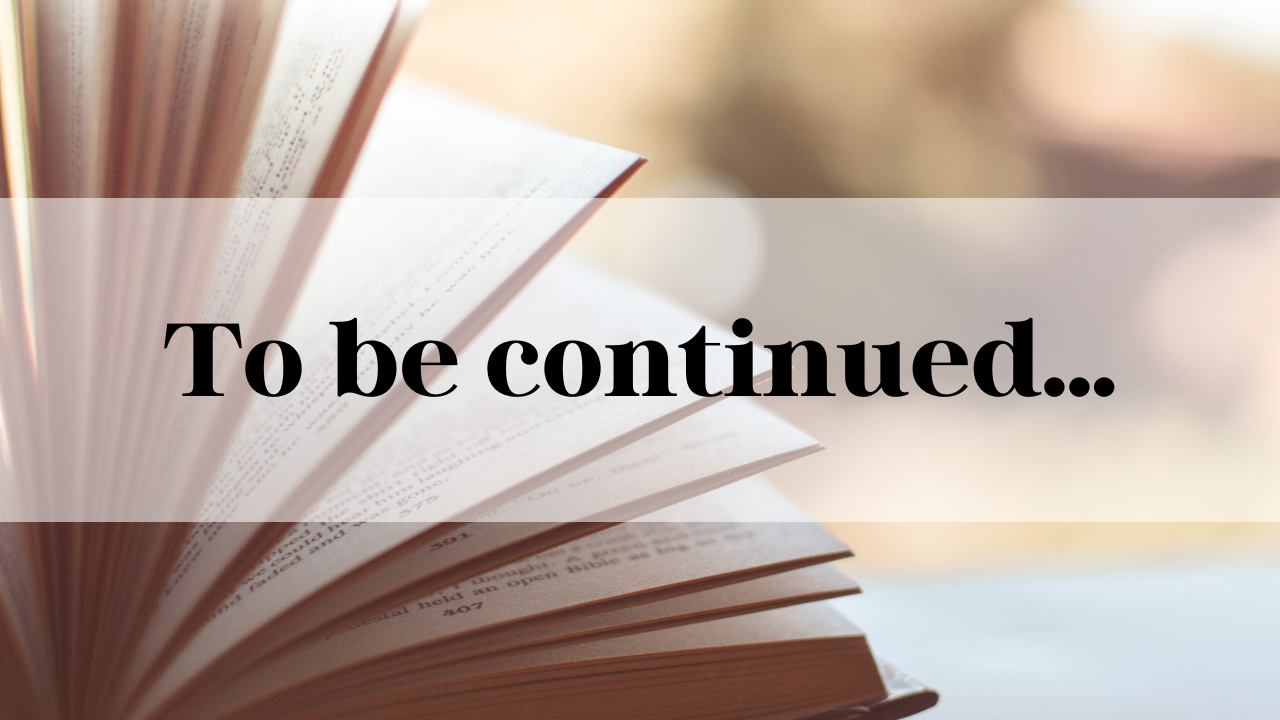
今回ご紹介した本はこちら☺︎(※広告)
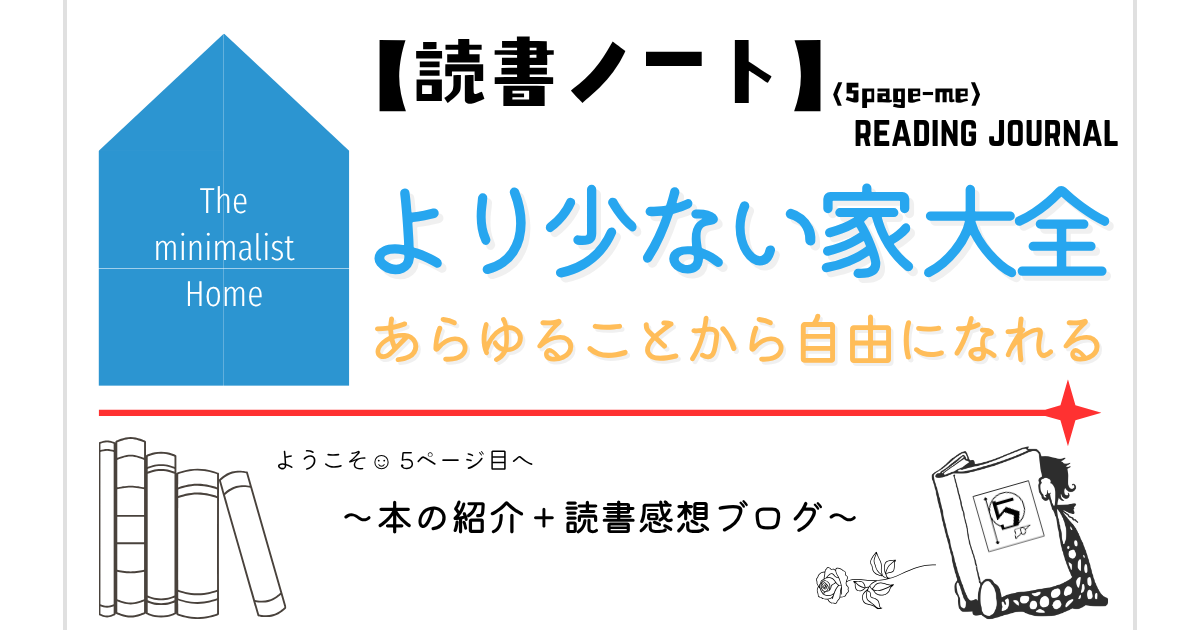

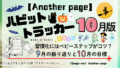
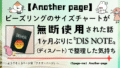
コメント